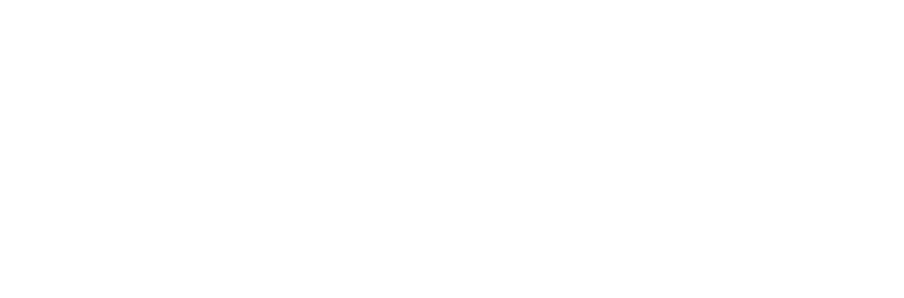2025年9月27日

「小児歯科で子どもが体を押さえられて治療された」と耳にすると、不安や戸惑いを感じる保護者の方も少なくありません。小さな子どもは、歯医者がどんな場所なのか分からず、治療器具や音に対して強い恐怖を抱くことがあります。そのため、治療中に体を動かしてしまうと、思わぬケガや治療の中断につながる可能性があります。こうした場面では、確実に治療を行うために、やむを得ず子どもの体を一時的に固定する「抑制(よくせい)」という対応がとられることがあります。今回は、小児歯科で抑制が用いられる理由や目的、その必要性、そして親としてできるサポートについて解説します。
1. 小児歯科で「抑制(体を押さえつける対応)」は必要?
歯医者で行われる「押さえつける」という行為は、医療用語では「抑制(よくせい)」と呼ばれ、子どもを守るために行われる医療的な対応のひとつです。以下に、治療中に抑制が行われる主な理由を紹介します。①治療中の事故を防ぐため
子どもが急に頭や手を動かすと、歯科器具が口の中を傷つける恐れがあります。体の動きを制限することで、思わぬケガを防ぎ、確実に治療を進める環境を整えることが目的です。
②治療回数をなるべく少なくするため
通院回数が多くなると、子どもにとって精神的な負担が大きくなります。抑制を取り入れることで、一度の来院で処置を終えることにつながり、負担を軽減できる場合があります。
③麻酔や薬剤の使用を減らす工夫
抑制を取り入れることで、鎮静や麻酔の使用を最小限にとどめられる場合があります。これは、子どもの体への負担をできるだけ少なくするための工夫のひとつです。
このように、抑制は必要最小限にとどめ、子どもの心身の状態に応じて歯医者が判断します。治療を進める際には、子どもの体への負担をできるだけ少なくするための方法のひとつとして用いられます。
2. 小児歯科で抑制(体を押さえつける対応)が必要になる理由
抑制は、すべての子どもに行われるものではなく、治療を適切に進めるために必要と判断された場合に限って行われます。ここでは、抑制が必要とされる代表的なケースとその理由を整理します。①年齢が幼く治療への理解が難しい場合
特に3歳未満の子どもは、治療の内容や目的を理解することが難しく、恐怖や不安から大きく動いてしまうことがあります。そのようなときには、体の動きを一時的に固定することで、処置を確実に進めやすくなる場合があります。
②過度に怖がって激しく動いてしまうとき
治療に強い不安を感じ、急に手足をばたつかせたり、頭を大きく動かしたりする子どももいます。このような動きがあると、器具が口の中を傷つけてしまうおそれがあるため、一時的に体を固定する対応が取られる場合があります。
③治療を急ぐ必要がある場合
外傷や急性の痛みがあるときには、症状の悪化を防ぐために、通常より早めの対応が求められると判断されることがあります。
④薬の使用に制限があるとき
麻酔や鎮静薬の使用に注意が必要な体質や持病がある場合には、体を一時的に固定することで薬の使用を最小限に抑えながら治療を進められる場合があります。
⑤何度も通院することが難しい場合
家庭の事情や子どもの精神的な負担を考慮し、短期間で治療を終えたい場合に、一度で処置を完了させるための方法として抑制が取り入れられることもあります。
抑制は、子どもの状態や治療内容に応じて慎重に判断されます。できる限り負担を少なくしながら、必要な処置を行うための対応のひとつといえます。
3. 小児歯科での心のケアと親にできるサポート
抑制をともなう治療は、子どもにとって身体的な負担だけでなく、心の面でも強いストレスになることがあります。子どもが歯科治療に前向きな気持ちを持てるよう、以下のような配慮が参考になる場合があります。
①治療をがんばったことをしっかり認める
治療の結果にかかわらず、「よくがんばったね」「最後まで座っていてえらかったね」など、行動そのものを認めてあげることで、子どもの自己肯定感を育むことにつながります。
②子どもの気持ちに寄り添う
「怖かったよね」「びっくりしたね」と、子どもの感情を受け止めることが大切です。無理に「大丈夫だったでしょ」と言わず、気持ちに共感することで、子どもの心が少しずつ落ち着いていくことがあります。
③歯医者に対する印象を少しずつ変える
「今度は○○先生に会えるね」「今日は何をするのかな?」など、前向きな言葉をかけることで、治療を特別な出来事ではなく日常のひとつとして受け止めやすくなります。
④家では無理に話をさせない
治療後は心が疲れていることもあります。子どもが話し出すのを待ち、気持ちを否定せずに受け止めることで、リラックスできる時間につながることもあります。
⑤親の気持ちも整理しておく
「かわいそうだった」「本当に必要だったのか」と感じることがあるかもしれません。けれど、治療の必要性を理解し、落ち着いた気持ちで子どもと接することが、次回以降の治療でも落ち着いて受けられる可能性があります。
子どもにとって、治療の内容と同じくらい大切なのが、その後の親の関わり方です。治療が嫌な記憶にならないよう、気持ちに寄り添った対応を意識してみることが大切です。
4. 上尾市の歯医者 たくみ歯科クリニックの小児歯科
上尾市の歯医者 たくみ歯科クリニックの小児歯科では、お子さんの成長発育に応じて、むし歯や歯肉炎の予防・治療を行っています。乳歯から永久歯への生え変わりを見据え、正しい歯みがき習慣や生活指導を通して、生涯にわたる健康な歯の基盤づくりをサポートしています。初めての歯科通院でもリラックスできるよう、優しい声かけと丁寧な診療を心がけています。
■ 当院の小児歯科ポイント①:子どもが安心できる診療環境づくり
お子さん・保護者ともに安心して通えるように明るく親しみやすい雰囲気づくりと、治療への不安を和らげられるように丁寧な説明で診療を行っています。
■ 当院の小児歯科ポイント②:むし歯を防ぐ予防処置が充実
フッ素塗布・シーラント・歯みがき指導など、むし歯予防に効果的な処置を定期的に実施。乳歯や生えたての永久歯をしっかり守ります。
■ 当院の小児歯科ポイント③:成長に合わせた継続的なサポート
歯並びやかみ合わせ、生活習慣まで含めた長期的な視点で、お子さんの将来の健康まで見据えたケアを提供しています。 お子さんの歯の健康は、将来の笑顔や生活の質に直結します。 上尾市の歯医者 たくみ歯科クリニックでは、お子さんとご家族に寄り添いながら、楽しく通える歯科医院を目指しています。まずはお気軽にご相談ください。
▼たくみ歯科クリニックの小児歯科の詳細はこちら
https://dc-takumi.com/medical/medical06/
まとめ
小児歯科で行われる「押さえつける治療」は、子どもが強く動いてしまう場面で、処置を円滑に進めるために選ばれることがある対応のひとつです。すべての子どもに必要なわけではなく、治療内容や当日の状態に応じて慎重に判断されます。抑制には身体的・心理的な負担がともなうため、治療後には子どもの気持ちに寄り添った対応や、保護者の前向きな関わりがとても大切になります。 小児歯科での治療について不安やお悩みがある方は、上尾市の歯医者 「たくみ歯科クリニック」までご相談ください。
監修:たくみ歯科クリニック
院長 荒木 拓道(あらき たくみ)
《経歴》
2009年3月 日本歯科大学新潟生命歯学部卒業
2009年4月 医療生協さいたま 生協歯科臨床研修医・入職
2010年3月 医療生協さいたま 生協歯科臨床研修終了
2015年4月 医療生協さいたま あさか虹の歯科
2016年4月 東京医科歯科大学歯学部付属病院 研修登録医
2017年3月 東京医科歯科大学歯学部付属病院 研修登録医終了
2019年4月 埼玉西協同病院歯科 歯科医局長
《資格・所属学会》
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
日本歯科放射線学会 歯科用CBCT認定医
厚生労働省認定 歯科医師臨床研修指導医
日本睡眠歯科学会
日本栄養治療学会
日本老年歯科医学会
日本障害者歯科学会