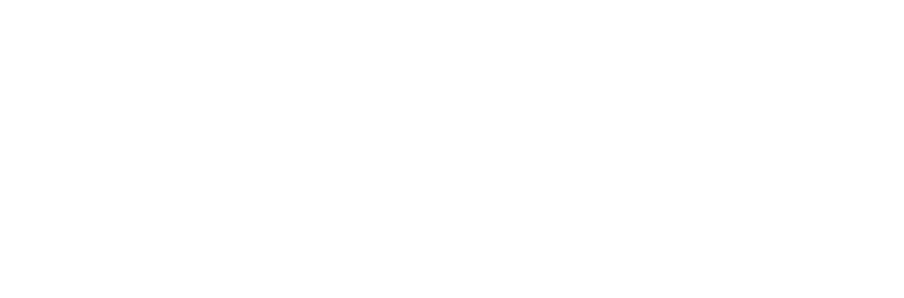2025年8月25日

子どもの歯が生え始めると、「いつから歯磨きを始めればいいの?」「ちゃんと磨けているのか心配…」と、不安になる保護者の方も多いのではないでしょうか。
特に、子どもが嫌がって歯磨きをさせてくれないと、毎日のケアがストレスに感じてしまうこともあるかもしれません。そんなときは、小児歯科での歯磨き指導を受けてみるのも一つの方法です。専門的なサポートを受けることで、子どもが無理なく歯磨きに慣れていき、むし歯予防につながる良い習慣を身につけることが期待できます。
今回は、小児歯科での歯磨き指導の開始時期や、家庭でのケア方法、子どもが前向きに取り組める声かけの工夫について解説します。
1. 小児歯科での歯磨き指導はいつから始まる?
歯磨き指導は、乳歯が生え始めたタイミングから受けることができます。具体的には、最初の乳歯が生えてくる生後6か月ごろから小児歯科の受診が推奨されており、その際に歯磨きの方法や注意点などについてアドバイスを受けることが期待できます。むし歯予防のためには、早い段階から正しいケアを始めることが大切です。ここでは、小児歯科で行われる歯磨き指導のポイントを解説します。①生後6か月頃から乳歯が生え始める
この時期は、下の前歯から少しずつ乳歯が生え始めるタイミングです。まだ歯ブラシは使わず、濡れたガーゼなどで歯を優しくぬぐう方法が推奨されることがあります。
➁1歳頃に歯ブラシによる清掃に移行する
上の前歯も生えてきたら、子ども用の小さくて柔らかい歯ブラシを使って、保護者が磨いてあげましょう。無理に磨こうとせず、まずは子どもに歯ブラシを持たせて遊ばせる・慣れさせるところから始めると、歯磨きがスムーズに進むことがあります。
③1歳6か月〜2歳ごろの歯科健診が目安に
多くの自治体では、1歳6か月健診や2歳児健診のタイミングで歯磨き指導が行われています。この頃には乳臼歯(奥歯)が生え始めるため、歯と歯の間までしっかり磨くことを意識することが大切です。仕上げ磨きの際は、奥歯まで歯ブラシがきちんと届くように心がけましょう。
④仕上げ磨きは小学校低学年頃まで
子どもが自分で歯磨きできるようになっても、仕上げ磨きはしばらく必要です。特に幼児期は、手先の動きがまだ未熟なため、どうしても磨き残しが出やすくなります。そのため、保護者による丁寧な仕上げ磨きがむし歯予防には欠かせません。
⑤歯医者での定期的なチェックが重要
磨き方の癖や、磨き残しがないかを歯医者で定期的に確認してもらうことで、早期にトラブルを防ぐことが期待できます。子どもにとっても、歯医者に慣れるよい機会となるでしょう。 小児歯科での歯磨き指導は、むし歯予防だけでなく、子どもが「自分の歯を大切にする意識」を育む第一歩です。
2. 小児歯科と連携して進める家庭での歯磨き方法
家庭での歯磨きは毎日のことだからこそ、しっかり行うことが大切です。小児歯科でアドバイスを受けながら、成長に合わせたケアを取り入れることで、むし歯予防の効果がより高まるでしょう。 ここからは、家庭でできる歯みがきのポイントを解説します。①子ども用歯ブラシとフッ素入り歯磨き粉を使う
毛先が柔らかく、ヘッドの小さい歯ブラシを選びましょう。フッ素入りの歯磨き粉は、歯の再石灰化を助け、むし歯を防ぐ効果が期待できます。使用量は年齢に応じて調整が必要です。
➁毎日の仕上げ磨きを習慣づける
子どもが自分で歯磨きをしたあとに、保護者が仕上げ磨きを行うことで、磨き残しを減らせる可能性が高まります。特に奥歯や歯と歯の間は汚れが溜まりやすい部分であるため、丁寧に磨きましょう。
➂就寝前の歯磨きを重視する
夜間は唾液の分泌が減少し、細菌が繁殖しやすくなります。寝る前にきちんと磨くことで、むし歯リスクを抑える効果があるとされています。
④定期的に小児歯科でプロのケアを受ける
家庭でのケアに加えて、3〜6か月ごとに歯医者で定期検診やフッ素塗布を受けることが大切です。専門的なチェックやクリーニングによって、家庭では気づきにくいむし歯のリスクにも早めに対応できる場合があります。 家庭でのケアと小児歯科での指導を組み合わせることで、子どもの口腔内環境をより良い状態で保つことが期待できます。
3. 子どもが歯磨き好きになるには?親の声かけのコツ
歯磨きを嫌がる子どもに対して、無理に口を開けさせたり、強い口調で注意したりすると、かえって歯磨きが苦手になってしまうことがあります。子どもが歯磨きを楽しい時間と感じられるようにするには、親の声かけが非常に大切です。ここでは、子どもが歯磨きを好きになるための親の声かけのポイントを解説します。
①成功体験を褒めて自信につなげる
子どもが自分で歯ブラシを持ったり、少しでも磨けたときは、具体的に「上手にできたね」「頑張ったね」と声をかけてあげましょう。こうした声かけで自己肯定感が育ち、次回も歯磨きを頑張ろうという気持ちにつながることがあります。
②「歯磨き=楽しい」と思わせる工夫
声かけの際には、「今日は歯がピカピカになる魔法の時間だよ」など、遊び感覚の表現を使うことで、子どもが興味を持ちやすくなります。ぬいぐるみやお人形に歯磨きをするふりをして見せるのも効果的です。
③選択肢を与えて自主性を引き出す
「今から歯磨きしよう」ではなく、「先に上の歯から磨く?それとも下からにする?」といった質問をしてみましょう。子どもが自分で選んだと感じることで、歯磨きに協力的になりやすくなります。
④タイミングに配慮した誘導を行う
眠くなる直前や機嫌の悪いタイミングで歯磨きを促すと、拒否される可能性が高まります。機嫌の良いときを見計らって「そろそろ歯をきれいにしようか」と、穏やかに声をかけましょう。
⑤子どもと一緒に磨くことでお手本になる
親が率先して楽しそうに歯を磨いている姿を見ると、子どもも「やってみたい」と感じることがあります。「ママと一緒にきれいにしようね」と誘い、親子のコミュニケーションの時間として活用しましょう。
➅毎日の習慣として自然に取り入れる
「今は歯磨きの時間だよ」と毎日のルーティンに組み込み、生活の中に歯磨きを定着させることが重要です。特別なことではなく、日常の一部として扱うことがポイントです。 子どもは親の言葉や態度から多くを学びます。焦らず、褒めながら寄り添う姿勢が、歯磨きを「イヤな時間」から「楽しい習慣」へと変えていく鍵となるでしょう。
4. 上尾市の歯医者 たくみ歯科クリニックの小児歯科
上尾市の歯医者 たくみ歯科クリニックの小児歯科では、お子さんの成長発育に応じて、むし歯や歯肉炎の予防・治療を行っています。乳歯から永久歯への生え変わりを見据え、正しい歯みがき習慣や生活指導を通して、生涯にわたる健康な歯の基盤づくりをサポートしています。初めての歯科通院でもリラックスできるよう、優しい声かけと丁寧な診療を心がけています。
■ 当院の小児歯科ポイント①:子どもが安心できる診療環境づくり
お子さん・保護者ともに安心して通えるように明るく親しみやすい雰囲気づくりと、治療への不安を和らげられるように丁寧な説明で診療を行っています。
■ 当院の小児歯科ポイント②:むし歯を防ぐ予防処置が充実
フッ素塗布・シーラント・歯みがき指導など、むし歯予防に効果的な処置を定期的に実施。乳歯や生えたての永久歯をしっかり守ります。
■ 当院の小児歯科ポイント③:成長に合わせた継続的なサポート
歯並びやかみ合わせ、生活習慣まで含めた長期的な視点で、お子さんの将来の健康まで見据えたケアを提供しています。 お子さんの歯の健康は、将来の笑顔や生活の質に直結します。上尾市の歯医者 たくみ歯科クリニックでは、お子さんとご家族に寄り添いながら、楽しく通える歯科医院を目指しています。まずはお気軽にご相談ください。
▼たくみ歯科クリニックの小児歯科の詳細はこちら
https://dc-takumi.com/medical/medical06/
まとめ
小児歯科での歯磨き指導は、生後6か月ごろから受けられることがあり、乳歯が生え始めたタイミングで始めるのが理想的です。家庭での毎日のケアはもちろん大切ですが、小児歯科と連携することで、子どもに合った方法を見つけやすくなります。また、親の声かけや関わり方ひとつで、歯みがきに対する子どもの印象が大きく変わることも少なくありません。 小児歯科や子どもの歯磨きについてお悩みの方は、上尾市の歯医者 たくみ歯科クリニックまでお問い合わせください。
監修:たくみ歯科クリニック
院長 荒木 拓道(あらき たくみ)
《経歴》
2009年3月 日本歯科大学新潟生命歯学部卒業
2009年4月 医療生協さいたま 生協歯科臨床研修医・入職
2010年3月 医療生協さいたま 生協歯科臨床研修終了
2015年4月 医療生協さいたま あさか虹の歯科
2016年4月 東京医科歯科大学歯学部付属病院 研修登録医
2017年3月 東京医科歯科大学歯学部付属病院 研修登録医終了
2019年4月 埼玉西協同病院歯科 歯科医局長
《資格・所属学会》
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
日本歯科放射線学会 歯科用CBCT認定医
厚生労働省認定 歯科医師臨床研修指導医
日本睡眠歯科学会
日本栄養治療学会
日本老年歯科医学会
日本障害者歯科学会