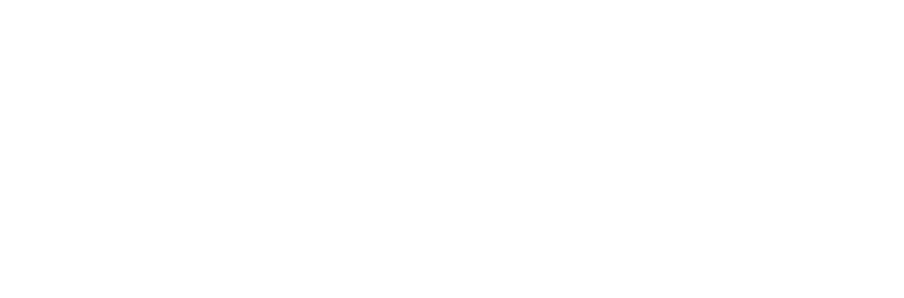2025年8月19日

お子さんの歯の健康は、将来の全身の健康や発育にも大きな影響を与える大切なポイントです。特に乳歯が生えている時期や、永久歯への生え変わりの時期は、虫歯予防や噛み合わせの管理が重要です。しかし、「歯が痛いと言っていないから、歯医者は必要ないかも」そんな風に思っていませんか?実は、痛みなどの症状が出てからではなく、予防のために定期的に通院することが大切です。今回は、4歳の子どもが歯医者に通い始めるべき理由や、小児歯科で受けられる虫歯予防の内容について解説します。
1. 4歳の子どもが歯医者に通い始める目安
子どもが歯医者に通い始める時期については、多くの親御さんが悩まれるポイントです。実は、4歳は予防のために歯医者に通院するのに適した年齢です。①乳歯がすべて生えそろう時期
4歳頃になると、乳歯は上下で合計20本がほぼ生えそろっています。この時期は、噛み合わせや歯の並びの基本が形成される重要な時期です。
②虫歯リスクが高まる年齢
お菓子やジュースなどの摂取が増え、歯磨きも「自分でやりたい」という気持ちが強くなる時期です。しかし、お子さんだけの歯みがきは汚れが残りやすく、虫歯のリスクが高くなります。この時期こそ仕上げ磨きの重要性が高まり、歯医者でのチェックも必要です。
③歯医者の環境に慣れやすいタイミング
この年齢は、はじめての環境にも少しずつ順応できるようになります。痛みや不安がないときに歯医者へ行くことで、歯医者への苦手意識を軽減し、将来の治療へのハードルを下げる効果も見込める場合があります。
④歯並びの乱れの早期発見が可能
永久歯が生えてくる準備として、あごの成長だけでなく、指しゃぶり・口呼吸などのクセが歯並びに影響を与える時期です。早めに歯科医師に相談することで、将来の矯正リスクを軽減する可能性があります。
⑤保護者の口腔衛生意識が高まる
定期的な通院によって、家庭での歯磨きや食習慣への意識が向上しやすく、お子さんの口腔環境をより良く整えるサポートにもなります。
このように、4歳は「予防」のスタートとして良いタイミングです。症状が出てからではなく、健康な状態のうちに通うことが歯の健康を守る第一歩となります。
2. 小児歯科での虫歯予防は何をしてもらえるの?
小児歯科では、虫歯ができてから治療するのではなく、虫歯をつくらないようにすることを目的とした予防中心のサポートが行われます。 特に4歳頃は、歯やお口の発達が進む大切な時期であるため、その成長段階に合わせた予防処置が取り入れられています。①フッ素塗布
フッ素は歯の表面を強くして、虫歯菌の出す酸に対する抵抗力を高めることが可能です。お子さんにも使用でき、定期的な塗布により、虫歯予防効果が期待できます。
②シーラント処置
奥歯の溝に専用の樹脂を埋める処置で、食べかすがたまりにくくなります。4歳頃は第一乳臼歯という奥歯が複雑な形をしており、この時期にシーラントをしておくと、虫歯になりにくくするサポートとして使用されることが多いです。
③歯磨き指導と仕上げ磨きチェック
お子さん自身の歯磨きスキルや、保護者の方による仕上げ磨きの状態を確認し、改善点を提案する場合があります。特に磨き残しの多い部分や歯並びの特徴を知るきっかけとなることがあります。
④食生活やおやつの指導
虫歯予防には、食事の取り方や間食の回数にも配慮が必要です。小児歯科では、保護者の方へのアドバイスも含めて、ご家庭での食習慣を見直すサポートが行われます。
⑤歯のクリーニング(PMTC)
専門の機器を使って、家庭では取りきれない歯垢や汚れを取り除きます。歯の表面を清潔に保つことに役立つ場合があります。
⑥歯の健康チェック
初期の虫歯や歯肉炎、噛み合わせのずれなどを早く見つけるために、定期的なチェックを行っています。もし気になることが見つかった場合は、その子に合ったタイミングで、治療や必要なケアを行います。
このように、小児歯科では虫歯予防に関する様々なケアが行われます。予防処置を定期的に受けることで、子どもの歯の健康状態を良好に保つことが期待できます。
3. 4歳ごろの歯並びに影響するクセとそのチェック方法
子どもの歯並びは、乳歯の時期から少しずつ形成されていきます。特に4歳頃は、骨や筋肉がやわらかく、日常的なクセが歯並びや顎の発育に大きく影響する時期です。お子さんの習慣や口元の様子を日頃から観察し、歯並びに影響するようなクセを早めに見つけて対処することが重要です。
①指しゃぶり
4歳でも続いている場合は要注意です。指がずっと歯やあごに当たることで、前歯が出たり、上下の歯がうまくかみ合わなくなる「開咬(かいこう)」と呼ばれる歯並びの乱れを引き起こすことがあります。こうした習慣が定着している場合は、早めに歯医者で相談し、無理のない対応方法を一緒に考えていくことが大切です。
②口呼吸
口を開けたままにしているクセがあると、唇や舌の筋肉のバランスが崩れ、出っ歯や歯列の乱れに繋がる可能性があります。慢性的な鼻づまりが原因のこともあるため、小児科や耳鼻科との連携も大切です。
③頬杖や寝るときの姿勢
いつも同じ方向を向いて寝る、頬杖をつく癖があるなどの外からの圧力も、顎の成長に影響を与えます。歯や顎に片側だけ力が加わると、噛み合わせのズレや顎の歪みに繋がるリスクがあります。
④舌のクセ(舌突出癖)
発音や飲み込みの際に舌を前に出すクセがあると、前歯が押されて前に傾く場合があります。これも開咬や出っ歯の原因となるため、早期の改善が重要です。
⑤哺乳瓶やおしゃぶりの長期使用
3歳以降も頻繁に使っている場合は、歯並びや噛み合わせへの影響が考えられます。使用を控えたり、段階的にやめる工夫が求められます。
⑥歯ぎしり
子どもの歯ぎしりは、成長の一部としてよく見られることもありますが、力が強かったり長く続いたりすると、歯やあごに影響することがあります。就寝中の様子を観察し、気になる場合は歯科医師に相談しましょう。
このようなクセは、最初はちょっとした行動でも、将来の歯並びやあごの成長に関わってくることがあります。気になる習慣があれば、早めに歯医者でチェックを受けることが、歯並びトラブルの予防につながるでしょう。
4. 上尾市の歯医者 たくみ歯科クリニックの小児歯科
上尾市の歯医者 たくみ歯科クリニックの小児歯科では、お子さんの成長発育に応じて、むし歯や歯肉炎の予防・治療を行っています。乳歯から永久歯への生え変わりを見据え、正しい歯みがき習慣や生活指導を通して、生涯にわたる健康な歯の基盤づくりをサポートしています。初めての歯科通院でもリラックスできるよう、優しい声かけと丁寧な診療を心がけています。
■ 当院の小児歯科ポイント①:子どもが安心できる診療環境づくり
お子さん・保護者ともに安心して通えるように明るく親しみやすい雰囲気づくりと、治療への不安を和らげられるように丁寧な説明で診療を行っています。
■ 当院の小児歯科ポイント②:虫歯を防ぐ予防処置が充実
フッ素塗布・シーラント・歯みがき指導など、むし歯予防に効果的な処置を定期的に実施。乳歯や生えたての永久歯をしっかり守ります。
■ 当院の小児歯科ポイント③:成長に合わせた継続的なサポート
歯並びやかみ合わせ、生活習慣まで含めた長期的な視点で、お子さんの将来の健康まで見据えたケアを提供しています。 お子さんの歯の健康は、将来の笑顔や生活の質に直結します。上尾市の歯医者 たくみ歯科クリニックでは、お子さんとご家族に寄り添いながら、楽しく通える歯科医院を目指しています。まずはお気軽にご相談ください。
▼たくみ歯科クリニックの小児歯科の詳細はこちら
https://dc-takumi.com/medical/medical06/
まとめ
4歳は、虫歯のリスクが高まり歯並びにも影響が出始める大切な時期です。小児歯科では、フッ素塗布やシーラントによるむし歯予防に加え、指しゃぶりや口呼吸などの習慣が歯並びへ及ぼす影響を確認できる可能性があります。家庭でも仕上げ磨きや生活習慣の見直しを行いながら、定期的に歯医者でのチェックを受けることで、お子さんの口腔内の健康を守りましょう。 上尾市周辺で小児歯科や虫歯予防、歯並びのチェックについてお悩みの方はたくみ歯科クリニックまでお問い合わせください。
監修:たくみ歯科クリニック
院長 荒木 拓道(あらき たくみ)
《経歴》
2009年3月 日本歯科大学新潟生命歯学部卒業
2009年4月 医療生協さいたま 生協歯科臨床研修医・入職
2010年3月 医療生協さいたま 生協歯科臨床研修終了
2015年4月 医療生協さいたま あさか虹の歯科
2016年4月 東京医科歯科大学歯学部付属病院 研修登録医
2017年3月 東京医科歯科大学歯学部付属病院 研修登録医終了
2019年4月 埼玉西協同病院歯科 歯科医局長
《資格・所属学会》
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
日本歯科放射線学会 歯科用CBCT認定医
厚生労働省認定 歯科医師臨床研修指導医
日本睡眠歯科学会
日本栄養治療学会
日本老年歯科医学会
日本障害者歯科学会